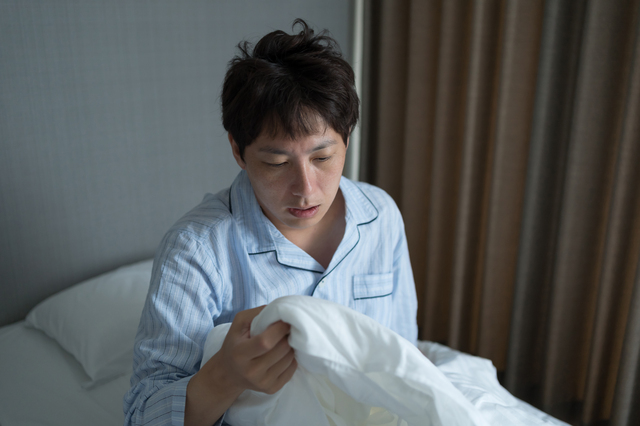止まらないあくびの原因とは?効果的な対処法を含めて解説!

「あくびが止まらないことが多いけど、何が原因なんだろう……」
「あくびが止まらないことがあるから対処法を知りたい……」
このような悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。
あくびは無意識に口を大きく開けて息を吸い込み、ゆっくりと吐き出す生理現象で、眠気や退屈を感じたときに起きやすいです。
一度あくびをすると、なかなか止まらない状態になってしまうこともあり、仕事や勉強に対する集中力が途切れてしまうケースも少なくありません。
そこで本記事では、あくびが止まらない原因や対処法について解説します。あくびが止まらないことが多い方は、参考にしてみてください。
目次
単なる眠気だけではない?止まらないあくびの原因

あくびが止まらない原因は、主に3つあります。
- 睡眠不足だけじゃない!睡眠の質が低下している可能性
- 脳の酸素不足・血流低下による影響
- 疲労の蓄積によって体が休息を求めている
それぞれの原因について解説します。
睡眠不足だけじゃない!睡眠の質が低下している可能性
7時間以上寝ていても眠気が収まらない・あくびが止まらないという方は、睡眠の質が低下している可能性があります。
たとえば、8時間程度寝ていても、夜中に何度も目が覚めてしまう場合や、浅い眠りが続くと、寝ているつもりでも脳や体は十分に回復できていません。
脳や体が十分に回復できていないと、疲労が蓄積していたり眠気を解消できていなかったりするため、日中に強い眠気や集中力の低下が起き、あくびが止まらない状態になります。
そのため、日中に強い眠気が訪れる方は、睡眠の質が影響している可能性があるため、睡眠習慣を見直すのがおすすめです。
脳の酸素不足・血流低下による影響
あくびが止まらない原因は、脳の酸素不足や血流の低下による影響が考えられます。
長時間のデスクワークで同じ姿勢を続けていると、肩や首の血流が悪くなり、脳に十分な酸素が届かなくなります。換気が不十分な部屋はくうきがこもりやすく、酸素が少ない状態になりやすいです。
酸素が不足している状態を補おうとして、あくびが頻発する場合があります。
疲労の蓄積によって体が休息を求めている
疲労の蓄積によって体が休息を求めている場合、あくびが止まらない状態になる可能性があります。
仕事が忙しくて休日も休めなかったり、家事や育児で睡眠時間を確保できていなかったりする状態が続くと、脳や体の疲労が慢性化します。
疲労が蓄積すると、体はこれ以上の活動を抑えて休んでほしいというサインを出すために、あくびが頻発しやすいです。単なる眠気ではなく、疲れを知らせる警告反応としてあくびが現れる場合がある点も把握しておきましょう。
自律神経とストレスによるあくびが止まらない原因

あくびが止まらない原因として、自律神経とストレスが関係している場合もあります。
次は、あくびと自律神経の関係や、ストレスがあくびを引き起こすメカニズムについて解説します。
あくびと自律神経の関係
自律神経は、活動モードの交感神経と、休息モードの副交感神経の2種類があります。
あくびは、交感神経と副交感神経が切り替わるタイミングで出やすいです。
朝起きた段階では休息モードの副交感神経が優位ですが、体を動かそうとすると活動モードの交感神経が刺激され、自然にあくびがでます。逆に大切な会議が終わった後、緊張から開放されて副交感神経が優位に働くため、自然にあくびがでやすいです。
そのため、自律神経が切り替わるタイミングであくびが出やすいです。
ストレスがあくびを引き起こすメカニズム
ストレスが高まると、交感神経が優位になり、心拍数や血圧が上がって体が緊張状態になります。
緊張や不安による影響で脳が過活動状態になってしまい、脳内の温度調整・過剰な興奮を落ち着かせるためにあくびが出やすいです。就職面接の待合室で緊張が高まると、眠くもないのにあくびが止まらない状態になる場合もあります。
スポーツ選手が自然直前に大きなあくびをして、ストレスによる緊張を和らげようとする場合もあります。
ストレスによる緊張や不安を落ち着かせるために、あくびが出る場合がある点も把握しておきましょう。
あくびを止める効果的な対処法

あくびを止める効果的な対処法は、主に3つあります。
- まずは十分な睡眠時間を確保する
- 昼間に短時間の仮眠を取る
- 自律神経を整えるための生活習慣改善
それぞれの対処法について解説します。
まずは十分な睡眠時間を確保する
あくびを止めるための対処法として、まずは十分な睡眠時間を確保しましょう。
あくびの最大の原因は、睡眠不足や睡眠の質の低下です。毎日4~5時間しか寝ていない場合は、7~8時間程度しっかりと睡眠を取ってみましょう。
また、睡眠の質を低下させないために、就寝前にスマホやパソコンのブルーライトを避け、暗く静かな寝室環境を整えましょう。睡眠時間の確保と睡眠の質を改善するだけで、日中のあくびを大幅に減らすことが可能です。
昼間に短時間の仮眠を取る
日中のあくびを止めたいときは、昼間に短時間の仮眠を取りましょう。
眠気やあくびが出るときは、脳が休息を求めているサインでもあります。
具体例を挙げると、昼休憩時に15~20分の仮眠を取ると、眠気を解消できるとともに午前中の疲労を回復できます。
また、仮眠前にコーヒーを飲んでおくと、仮眠から目が覚めるタイミングでカフェインによる覚醒作用が現れやすいです。短い休息で脳の疲れをリセットできるため、午後のあくび防止につながります。
自律神経を整えるための生活習慣改善
自律神経の乱れは、あくびが止まらない原因の一つでもあるため、生活習慣の改善を図りましょう。
朝はカーテンを開けて自然光を浴びることで、体内時計を整えられます。また、デスクワークの合間に軽いストレッチや深呼吸を行うことで、自律神経のリセットや血流改善が期待できます。
ほかにも、適度な運動や入浴を行うことで、副交感神経が優位になりやすく、夜の睡眠の質が上がりやすいです。自律神経を整えることで、脳や体のリズムが安定し、あくびが頻発する状態を抑えられます。
まとめ
あくびが止まらない状態は、眠気だけでなく脳が休息を求めているサインの可能性があります。とくに生活習慣が乱れていると、自律神経が乱れてしまい、睡眠の質の低下や体・脳のバランスの崩壊を招きます。
午後にあくびが止まらないという方は、昼休憩時に15~20分程度の短い仮眠を取ると、眠気解消と合わせて疲労回復を促せるためおすすめです。
あくびが止まらない方は、本記事で紹介した内容を参考に、生活習慣の改善を図ってみてください。
誰もが理想的な休息を「giraffenap(ジラフナップ)」

最適な仮眠環境を構築したいときは、弊社 広葉樹合板の立ったまま眠れる仮眠ボックス「giraffenap(ジラフナップ)」がおすすめです。
小型の公衆電話ほどのサイズで、理想的な姿勢・環境下で仮眠を取ることができます。
ジラフナップの中は遮音性に優れているほか、適度な暗さを保つ設計です。

また、どこにも力が入らない4点保持の姿勢で眠れるように開発しており、立ったままでも理想的な眠りにつけます。
ベッドを置く部屋を作る必要がない上に、眠気が訪れた際に気軽に仮眠を取れる環境を構築できるため、従業員の健康増進やパフォーマンス向上が期待できます。
製品の詳細や導入に関するお問い合わせについては、どうぞお気軽にご相談ください。あなたの職場に最適な仮眠環境をご提案いたします。

 日本語
日本語